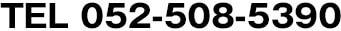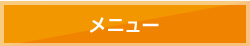全国ネットワーク


コラム
2025.01.20
ヒヤリハット撲滅!軽貨物ドライバーのための安全運転ガイド

ヒヤリハットとは?なぜ撲滅が必要なのか
ヒヤリハットとは、「ヒヤリ」としたり「ハッ」としたりする、事故寸前の出来事です。
幸いにも事故には至らなかったものの、放置すれば重大な事故につながる可能性を秘めています。
労働災害の分野では「ハインリッヒの法則」が広く知られており、1件の重大事故の裏には29件の軽傷事故、さらにその背景には300件ものヒヤリハットが存在するとされています。
この法則が示唆するのは、300件のヒヤリハットに目を向け、分析し、対策を講じることによって、重大事故を効果的に予防できるということです。
特に、軽貨物運送業では、運転中のヒヤリハットはもちろんのこと、荷物の積み下ろし作業時、駐車時、歩行者や自転車との接触など、さまざまな状況でヒヤリハットが発生し得ます。
例えば、急いで配達に向かう途中で、信号無視をしそうになった、荷台の荷物が崩れそうになった、狭い道で対向車とすれ違いでヒヤリとした、といった経験はないでしょうか。
これらはすべてヒヤリハットであり、重大事故につながる可能性を秘めた重要なサインです。
これらの小さな危険を見過ごさず、一つ一つ丁寧に対策を講じることが、安全な業務環境の構築、ひいては自身の安全、会社の安全へと繋がります。
だからこそ、ヒヤリハットを撲滅するという強い意識を持つことが重要なのです。
軽貨物ドライバーが遭遇しやすいヒヤリハット事例
軽貨物ドライバーが遭遇しやすいヒヤリハットは、日々の業務の中で様々な形で現れます。
以下に具体的な事例を挙げます。
運転中
交差点での右左折時
歩行者や自転車の巻き込み、対向車との衝突。特に、急いでいる時や見通しの悪い交差点で発生しやすい。
急な飛び出しや割り込み
歩行者、自転車、他の車両の急な動きに対応しきれず、急ブレーキを踏む。
悪天候時の視界不良
雨天、濃霧、夜間など、視界が悪い状況で歩行者や障害物を見落とす。
駐車・停車時
周囲の車両や障害物との距離感がつかめず、接触。特に狭い場所や時間制限のある状況で焦ってしまいやすい。
長距離運転による疲労
集中力や判断力の低下により、危険に対する反応が遅れる。
スマートフォン等の使用
運転中の「ながらスマホ」は、周囲の状況への注意力を著しく低下させ、重大な事故につながる可能性が高い。
荷物の積み下ろし時
重量物の持ち運び
腰痛、ぎっくり腰、荷物の落下による怪我。
足場の不安定な場所での作業
転倒、荷物の落下。
荷崩れ
積み方が不適切で荷物が崩れ、周囲の人や物に危害を加える。
配送先での移動中
階段や段差でのつまずき
荷物を持ちながらの移動は特に危険。
配送先での予期せぬ出来事
犬に追いかけられる、不審者との遭遇など。
これらの事例は、軽貨物ドライバーが日常的に遭遇しうるヒヤリハットの一部です。
これらの事例を共有し、注意喚起することで、事故を未然に防ぐことが重要です。
ヒヤリハット撲滅のための具体的な対策
ヒヤリハットを撲滅するためには、ドライバー個人の意識改革と、会社全体での組織的な取り組みが不可欠です。
以下に具体的な対策を挙げます。
ドライバー個人の対策
出発前点検の徹底
ブレーキ、ライト、タイヤ、荷物の固定状況などを確認。
安全運転の基本徹底
法定速度の遵守、十分な車間距離の確保、交差点での安全確認。
危険予測運転
周囲の状況を常に把握し、危険を予測して行動する。
疲労管理
十分な睡眠と休憩を取り、無理な運転を避ける。
運転中のスマホ等使用禁止
運転に集中する。
会社全体の対策
安全教育・研修の実施
定期的な安全教育やヒヤリハット事例の共有。
ヒヤリハット報告制度の確立と周知
報告しやすい環境づくりと、報告内容の分析と対策への反映。
安全装備の導入
ドライブレコーダー、バックモニター、衝突被害軽減ブレーキなどの導入。
無理のない運行計画
余裕を持った配送スケジュールの設定。
安全管理体制の強化
安全管理責任者の配置、安全委員会の設置など。
これらの対策を徹底することで、ヒヤリハットの発生を大幅に減らし、事故のない安全な業務環境を実現することができます。
ヒヤリハット撲滅には、ドライバーと会社が一体となって取り組むことが重要です。
ヒヤリハット報告の重要性と効果的な活用方法
ヒヤリハット撲滅は、単に事故を減らすだけでなく、ドライバー自身の安全と健康を守り、会社の社会的責任を果たし、社会全体の安全に貢献するという大きな意義があります。
軽貨物運送業界全体でヒヤリハット撲滅に取り組むことで、より安全で信頼性の高い物流サービスを提供することが可能になります。
日々の業務において、常に安全意識を持ち、ヒヤリハットを減らす努力を継続していくことが、軽貨物運送に携わるすべての人々に求められる重要な責任です。
安全第一の意識を常に持ち、ヒヤリハット撲滅に向けて積極的に行動していきましょう。この意識こそが、安全な社会の実現に繋がる重要な一歩となるのです。
-
2024.09.05
-
2024.08.30
×
カンタンお見積り ▲